記事の著者
マーケティングチーム

一生に一度の高い買い物といわれるマイホーム。しかし、優遇制度を活用することで、経済的な負担は軽減されます。中でもマイホームの新築や取得を検討している方にとって、利用しやすいのが住宅ローン控除です。最大13年間にわたって所得税や住民税が軽減されるため、経済的なメリットは計り知れません。しかし、制度の延長は2025年末までの予定となっており、駆け込みでの利用を検討する方も増えているようです。
そこで本記事では、住宅ローン控除について詳しく紹介し、適用条件や注意点などについても解説します。住宅の取得・購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
ハウスジャパンは、1983年創業以来、地域に根ざした家づくりを通じて、お客様の「本当の思い」を丁寧に引き出し、心から豊かな暮らしを形にするパートナーです。
多彩なデザインラインナップを持ち、それぞれの家族のライフスタイルに寄り添った提案を。
気候風土を熟知した地元密着体制と確かな技術で、住まいの安心・快適を長く支えるアフター対応も万全。
あなたと地域の未来をつなぐ、一生の住まいづくりをサポートします。

住宅ローン控除とは、所得税・住民税から住宅ローンの残高に応じた金額を差し引く制度です。「住宅ローン控除」のほか「住宅ローン減税」という呼び方もされますが、正式な名称は「住宅借入金等特別控除」です。
具体的には、マイホームを取得・新築・増改築した年から、その年末のローン残高の一定割合を翌年の所得税(所得税から控除しきれない分は住民税)から控除する仕組みです。現行制度では、控除できる期間は入居した年から最長で13年間、税金から控除できる額は年末時点での住宅ローン残高の0.7%です。
仕組みや適用条件は改正や見直しが行われており、現在は長期優良住宅や省エネ基準適合住宅といった4つの住居の種類に合わせて控除期間や借入限度額などが設定されています。

住宅ローン控除を受けると、節税などのメリットがある一方、デメリットもあります。メリットとデメリットについて、それぞれ詳しく解説します。
住宅ローン控除を受ける最大のメリットは節税効果です。住宅ローン残高に応じて、税金の支払額が数万円~数十万円控除されます。経済的な負担が軽減されるため、マイホームが取得しやすくなったり、予算をややオーバーできるといったことも考えられます。
また適応期間中は、税金が減額となった分を生活費や子どもの教育費、レジャー費、貯蓄などに回せるほか、長期的な資産形成にも役立ちます。
住宅ローン控除を受けるデメリットといえるのは、申請するための手続きが必要なことです。特にサラリーマンの方は、住宅を取得して1年目は通常する必要がない確定申告をしなければならないため、時間や労力を費やすことになります。適用条件に合致しているかを証明する書類をそろえることも必要です。
また住宅ローン控除には、制度上の制限があることにも注意しましょう。期間でいえば最長で13年間ですが、住宅ローンを活用して新築住宅を購入する場合、返済期間は20年以上になることもあります。つまり、住宅ローン控除の適用期間が過ぎた後は、メリットがなくなるのです。そのため、長期的な視点で住宅ローンの返済計画を立てるようにしましょう。
住宅ローン控除は、取得する住宅別に適用条件や控除額などの仕組みが異なります。「新築住宅」「買取再販住宅」「中古住宅」「増改築」の4つに分けて解説します。
新築住宅を取得した場合、2025年12月31日までに入居を開始した場合に住宅ローン控除が適用になります。以下が代表的な適用条件です。
また、控除額は住宅の区分によって異なります。新築で2025年を居住年とした場合の控除率や控除期間などを以下の表にまとめましたので確認してください。
| 住宅の区分 | 控除率 | 控除期間 | 借入限度額 | |
| 認定住宅等(新築) | 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 0.7% | 13年 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円
そのほかの世帯:4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 0.7% | 13年 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円
そのほかの世帯:3,500万円 |
|
| 省エネ基準適合住宅 | 0.7% | 13年 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円
そのほかの世帯:3,000万円 |
|
| そのほかの住宅 | 0.7% | 10年 | 0万円(2,000万円) | |
なお、そのほかの住宅の場合、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅で、2024年・2025年に入居する場合は、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。建売住宅を購入する場合、建築確認の日付や建築年月日も確認しましょう。
買取再販住宅とは、宅地建物取引業者などが住宅を取得してリフォームやリノベーションなどを施して販売している住宅のことです。リノベーション住宅やリフォーム済み住宅などとも呼ばれますが、中古住宅の一種です。
住宅ローン控除の代表的な適用条件は、新築住宅で示されている①~⑤の適用条件に加えて以下になります。
・その住宅が新築された日から起算して10年以上経過したものであること
・宅建業者が取得してリフォーム工事を行い、再販売するまでの期間が2年以内であること
・工事に要した費用の総額が、建物価格の20%に相当する金額(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること など
また、控除額は住宅の区分によって以下のようになっています。
| 住宅の区分 | 控除率 | 控除期間 | 借入限度額 | |
| 認定住宅等 | 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 0.7% | 13年 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円
そのほかの世帯:4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 0.7% | 13年 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円
そのほかの世帯:3,500万円 |
|
| 省エネ基準適合住宅 | 0.7% | 13年 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円
そのほかの世帯:3,000万円 |
|
| そのほかの住宅 | 0.7% | 10年 | 0万円(2,000万円) | |
控除率または控除期間などは、2025年を居住年とした場合のものです。
この場合の中古住宅とは、買取再販住宅を含まない、仲介などの方法で売買される通常の中古住宅のことです。住宅ローン控除が適用されるには、新築住宅で示されている①~⑤に加えて以下の条件が満たされている必要があります。
・新耐震基準に適合している(登記簿上の建築日が1982年1月1日以降)住宅であること
・居住した年とその前2年の計3年間で居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない など
また、控除額は住宅の区分によって以下のようになっています。
| 住宅の区分 | 控除率 | 控除期間 | 借入限度額 | |
| 認定住宅等 | 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 0.7% | 10年 | 3,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 0.7% | 10年 | 3,000万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 0.7% | 10年 | 3,000万円 | |
| そのほかの住宅 | 0.7% | 10年 | 2,000万円 | |
借入限度額は、認定長期優良住宅等が3,000万円、そのほかの住宅が2,000万円です。なお、控除期間はどちらも10年間です。
住宅ローンを契約してマイホームの増改築をした場合も、住宅ローン控除の適用を受けることができます。主な適用条件は以下になります。
・増改築後の家屋の床面積が50m2以上、床面積の2分の1以上が所有者自身が居住する住宅
・工事費用が100万円超で、そのうち2分の1以上の額を所有者自身の居住する住宅部分に使用すること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・増改築の内容は、床や壁などの修繕や模様替え、新耐震基準に適合させるために行う工事、バリアフリー工事、省エネ改修工事 など
増改築の場合、借入限度額は2,000万円、適用期間は10年間、控除率は0.7%です。
実は、現行の住宅ローン控除は2025年度で終了する予定です。つまり、2025年12月31日までに入居することができないと、住宅ローン控除を受けられないのです。住宅の取得を予定している方は、早めに準備するようにしましょう。
ただし、2026年度の税制改正に対する国土交通省からの要望項目には住宅ローン控除の継続が盛り込まれており、2025年9月時点では未定ですが、住宅ローン控除が継続される可能性もあります。住宅の取得を予定している方は最新の情報を確認しましょう。
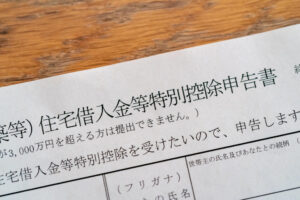
住宅ローン控除を受ける際の注意点について、代表的な4つを紹介します。
住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅に入居した翌年に確定申告を行う必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得の金額と、それに対する所得税額を申告する制度です。一定額以上の事業所得がある自営業やフリーランスなどの個人事業主が、所得税額などを申告するために行っています。
会社勤めをしているサラリーマンなどは、経理担当者が納税業務を行うのが通常です。そのため、住宅ローン控除を申請する際に初めて確定申告を行うという方が多く、慣れない作業に苦労するケースも多いようです。
なお、確定申告を行う際、必要となるのが以下の書類です。
・マイナンバーが記載された書類の写し
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・土地・家屋の登記事項証明書
・不動産売買契約書や工事請負契約書の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
また住宅の区分に応じて提出する書類も異なりますので、注意しましょう。
| 認定住宅等の区分 | 提出する書類 |
| 認定長期優良住宅 | ・都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」の写し
・市区町村の「住宅用家屋証明書」またはその写し、または建築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」 |
| 低炭素建築物 | ・都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し
・市区町村の「住宅用家屋証明書」またはその写し、または建築士等が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」 |
| ZEH水準省エネ住宅 | ・ZEH水準への適合を証する建設住宅性能評価書の写し |
| 省エネ基準適合住宅 | ・省エネ基準への適合を証する住宅省エネルギー性能証明書の写し |
1年目に確定申告を行った場合、2年目以降は会社で行っている年末調整で住宅ローン控除が適用されます。その際、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」や「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」といった書類を会社の経理担当者に提出することになります。
住宅ローン控除を受ける際は、借入先にも注意が必要です。借入先は以下の6つのいずれかであることが適用条件になっているからです。
・銀行
・農協、信用金庫、信用組合
・住宅金融支援機構
・地方公共団体
・各種公務員共済組合
・勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上であること)
例えば、親族や知人などの個人からお金を借りる場合、自身が役員となっている企業あるいは親族の会社からの借入金には住宅ローン控除は適用されません。
住宅に関わる税制にはさまざまなものがあり、住宅ローン控除と併用できないケースもあります。例えば、特定居住用財産の買換え特例や3,000万円特別控除が適用される場合、住宅ローン控除は適用されません。
代表的なものを以下にまとめていますので、確認してください。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
・居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2) など
なお、ふるさと納税と住宅ローン控除の併用はできますが、確定申告の必要がない「ワンストップ特例制度」は利用できません。ワンストップ特例制度の申請をした後で確定申告をした場合は、申請が無効になります。
住宅ローン控除を含む税制は毎年見直され、12月中旬ごろに翌年度の骨組みが発表されます。そのため、最新の情報を常にチェックしましょう。
現状では住宅ローン控除は今年度で終了する予定ですが、前述したように住宅ローン控除の継続、あるいは新規の税制制度が開始される可能性もあります。また、控除率や控除期間が見直される可能性もあるため、必ず確認しましょう。
本記事では、住宅ローン控除の適用条件や注意点、控除できる額などについて解説しました。節税効果が大きく、家計の負担も軽減されるなど、住宅を取得する際には大きなメリットとなります。
ただし、現状では2025年12月31日までに新居に入居しなければ住宅ローン控除を適用することができません。適切に判断し、マイホームの取得を検討してください。
なお、ハウスジャパンが提供する住宅は、すべて長期優良住宅認定の基準を満たしています。そのため、住宅ローン控除を受けるのに適した住宅です。
住宅ローン控除などの税制にも精通したスタッフが相談に応じていますので、不明な点などがあればお気軽にご相談ください。